信用取引とは
現物取引と信用取引の違い
一般的な株取引ではトヨタ株欲しければ証券会社に買い注文を出し、成立すれば株券を現金と引き替えに受け取ります。このようにお金と株券という現実にある物を、その都度やり取りする取引方法を「現物取引」と言います。
信用取引では、事前に担保を証券会社に入れておき、返済期限を決めた上で証券会社からお金を借り、そのお金で株を売買します。借りた購入代金は売却し、売却代金を受け取った時に精算します。このような現物のやり取りをせず、売り買いした代金を精算する決済方法を「差金決済」と言います。
証券市場には売り手と買い手により価格形成させる、価格形成機能という役割があります。それは参加者(流入する資金)が多ければ多いほど、より公正な価格形成が期待出来るのです。
市場の厚みを持たせるため、現物取引だけでなく、
- 即座にお金を用意出来ないが買いたい
- 手元に株券は無いが、下落しそうなので売っておきたい
といった売買もあった方がより効果的です。現物取引のように現物での需要を「実需」、信用取引の需要を「仮需(かりじゅ)」と言い、実需だけでなく仮需も導入されることで、価格形成がより公正に、証券市場がより使いやすくなっているのです。
もう1つ、信用取引には現物取引ではできない「ループトレード」を行えるメリットがあります。現物取引において、同一受渡日における同一銘柄(同一資金)の取引は、差金決済に該当する可能性があり、法令で禁止されています(行うとループトレード拘束金として株式買付代金相当額を拘束される)。
ループトレードはデイトレード(日計り取引)と言い換えてもいいでしょう。もしデイトレードをやりたいなら(1日に何度も同一銘柄の売買)、信用取引を活用しましょう。信用取引は原則、何度でもループトレード可能です。
信用取引の買い
信用取引で株を買う事を「信用買い」、売る事を「信用売り」と言います。まず信用買いから解説します。
信用買いは証券会社から購入資金を借りて株を購入します。その資金の返済方法は2つあります。一つは、買った株を売る反対売買で、売って受け取る売却代金と借りた購入代金とコストを差金決済します。基本的にはこちらが主です。
もう一つは、購入株を代金を支払い引き取る方法で、これを「現引き」と言います。こちらは、Aの株を買いたいが今は資金が無い。暫くすれば用意できるが、その時には買い時を逃してしまうという時に、借金で株を買い、お金が用意出来たら購入する方法です。
信用取引の売り
信用買いはお金さえあれば現物取引でも可能ですが、現物取引では絶対に出来ないのが「信用売り」です。
信用売りを簡単に言うと、「持ってもいない株を売る取引」です。どうやるのかというと、売る株を証券会社から借りて売るのです。持っていない株を売るので「空売り」とも呼ばれます。
借りた株の返済方法は2つあり、1つは借りて売った株を買い戻し、それを返済する反対売買です。普通、株は値上がりを期待して購入しますが、最初に売って後で買い戻すわけですから、対象の株が「値下がりすると利益が出る」のです。
現物取引の収益機会は値上がりしか期待出来ませんが、信用取引を使うと値下がりも収益機会として活用できます。市場が上昇局面だけでなく下降局面でも利益が狙えるのが信用取引の特徴です。
もう一つの返済方法は、信用売りした銘柄と同じ現物株を持っている場合、それを借りた株の返済に使う方法で「現渡し」と言います。
他にも「つなぎ売り」という手法で信用売りを利用できます。これは持っている株と同じ銘柄を信用売りするという手法です。何のためにそんな事をするのでしょうか。
例えば、A株を持っているが値下がりしてきた。しかし、この株は手放したくない。そういった時に同じ銘柄を信用売りする事で、保有現物株の方は含み損が出ますが、信用売りしている方は含み益が出るため合算すればチャラ。つまり、価格変動に対するヘッジです。
信用売りした時に借りた株を自分の保有現物株で返済すれば、事実上、保有現物株は信用売りした時点で売却したのと同じ意味になります。このような実際に手放すまでのつなぎとして利用する信用売りのため、つなぎ売りと呼ばれています。
信用取引はレバレッジが掛けられる
信用取引では、証券会社に預け入れる資金(委託保証金)の約3倍までお金を借りられます。つまり、自己資金の約3倍のレバレッジを掛けられます。また、担保は現金だけでなく上場株式も担保として利用できます。
現金はそのままの額で評価されますが、上場株式は一般に時価の8掛けで評価されます。100万円を委託保証金として預ければ、約300万円の取引が可能。上場株式を担保にした場合、時価が100万円なら約240万円分の取引が可能になります。
担保の金額ですが、取引額に対して「委託保証金率」と呼ばれる割合の額に相当する担保が必要になります。委託保証金率は証券会社により異なりますが、多くは30%程度です。例えば、100万円分の取引をするには、最低でも30万円分の担保が必要なります。
逆に言うと、30万円分の担保を預ければ100万円分の取引が可能になります。そこから約3倍の取引が可能という意味になります。委託保証金率は証券会社のWebサイトに書かれており、100万円の保証金で委託保証金率30%なら、
100万円 ÷ 0.3 = 約333万円
です。どれだけお金を借り入れるかは自分で決めます。
信用取引の税金
信用取引の売却益に掛かる税金は一般取引と全く同じです。
制度信用取引と一般信用取引の違い
制度信用取引とは
信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。まず制度信用取引から解説しましょう。
制度信用取引は、昭和26年に信用取引制度がスタートした時から続く取引で、現在でもこちらが信用取引では主流となっています。制度信用取引の特徴は、
- 返済期限がある
- 売買出来る対象銘柄が決まっている
が挙げられます。
制度信用取引では、「返済期限は最長で6ヶ月」と決められています。例えば1月1日に信用取引の注文が約定した場合、6月1日までに反対売買をするか、現引きしなければなりません。6ヶ月後にあたる日が休日の場合は、その前の営業日が期限になります。
制度信用取引には購入出来る銘柄と出来ない銘柄があり、購入出来る銘柄を「制度信用銘柄」と言います。対象銘柄は取引所が決定し、いわば取引のお墨付きを受けた銘柄といえます。
制度信用取引と証券金融会社
制度信用取引で信用買いや信用売りを顧客が注文した時、必要となるお金や株券を証券会社はどうやって調達しているのでしょうか? それは証券金融会社から融通してもらっているのです。
証券金融会社とは、証券会社が投資家に融通する資金や株が足りない時、その分を証券会社に有料で貸し出す業務(貸借取引)を行う会社です。日本では日本証券金融、大阪証券金融、中部証券金融などがあります。
制度信用銘柄に関しては、証券金融会社が信用買いの注文を仲介する証券会社にお金を貸してくれます。さらに、制度信用銘柄の「貸借取引」の対象に指定されている銘柄、貸借銘柄は、証券金融会社が証券会社に株券を貸してくれます。これにより制度信用取引は、信用買い・信用売りに対応出来るのです。
では、実際どのような流れでやり取りされているのか説明しましょう。
Aという銘柄を信用買いしている人と、信用売りしている人がいたとします。信用買いした人はお金を借り株を買ったわけですから、本来なら株券を受け取るはずです。しかし、実際は信用買いした人の元に株券は渡りません。
一方、信用売りした人は借りた株券を売ったのですから、本来なら売却代金を受け取るはずです。しかし、信用売りした時点では受け取れないのです。こういった株券や売却代金はどうなっているのでしょうか?
同一証券会社内において、信用買いした人は同じ銘柄を信用売りした人に、購入株券を貸した状態になっているのです。結果、同一証券会社において、買いで必要になるお金と売りで必要になる株券は、ある程度相殺(店内食い合い)する事が出来ます。
店内食い合いで賄い切れないお金、株券については、証券会社が賄えるなら貸し、無理なら証券金融会社から借りる事になります。投資家が信用取引を行う時、内部ではこのような事が起こっているのです。
貸借銘柄とは
貸借銘柄とは、証券金融会社から証券会社が株券を借りられる銘柄、つまり、信用売り出来る銘柄となります。そうなると、制度信用取引の対象銘柄には、以下の2つがあることが分かります。
- 制度信用銘柄で、貸借銘柄であるもの
- 制度信用銘柄で、貸借銘柄ではないもの
制度信用銘柄であり、貸借銘柄でない銘柄というのは、証券金融会社から証券会社が、信用買いに対応するためにお金は借りられるが、信用売りに対応するための株券は借りられない銘柄です。
信用取引(制度信用)では、全ての銘柄が買えるわけでもなく、さらに全ての銘柄が空売り出来るわけでもないのです。これは覚えておきましょう。
新聞の株式欄には、貸借銘柄には銘柄名の頭に「・」がついています。
一般信用取引とは
一般信用取引は、返済期限や品貸料など取引のルールを、投資家と証券会社で決める事が出来る信用取引を指します。一般信用取引は1998年に解禁されました。
- 取引ルールが証券会社が決める
- 対象銘柄は上場銘柄全て(整理ポスト銘柄など例外あり)
- 基本的に空売り出来ない
一般信用取引は投資家と証券会社でルールを決めるため、例えば返済期限も制度信用より早い3ヶ月であったり、返済期限の無い無期限信用取引というものも存在します。
対象銘柄は基本的に「上場銘柄全て」になります。対象銘柄が限られている制度信用よりも有利な点です。
一般信用と制度信用との一番の違いは、一般信用取引では証券金融会社から、お金や株券を借りる事が出来ない点です。特に大きく影響するのが「株券を借りられない」という点であり、これは「信用売りが出来ない」事を意味しています。
一部の証券会社では、一部銘柄は一般信用取引の信用売りが可能な所もありますが、基本的には出来ないという認識で間違いありません。
一般信用と制度信用の比較
| 制度信用 | 一般信用 | |
|---|---|---|
| 返済期限 | 6ヶ月。 | 無期限など、各証券会社が独自に決める。 |
| 対象銘柄 | 取引所が指定する銘柄に限定される。 | 基本的に上場している全ての銘柄。 |
| 信用売り | 制度信用の対象銘柄中の貸借銘柄のみ。 | ほとんどの証券会社で信用売り不可。 |
| 資金や株券の調達方法 | 独自調達と証券金融会社から借り入れる。 | 独自調達のみ。 |
お金を借りる以上、金利を支払う事になります。これを「買い方金利」と言います。制度信用と一般信用を比べると、制度信用の方が一般信用より金利が安いのが普通です。ネット証券などでは、制度信用の金利は約2.8%~3.0%、一般信用の金利は約3.1%~3.6%となっています。
基本的に一般信用は信用売り出来ないため、空売りしたい場合は制度信用を利用するしかありません。他には制度信用は最長6ヶ月で決済しなければなりませんが、一般信用は無期限です。
これらから考えるに、一般信用を利用するのは、
- 制度信用の対象銘柄でない銘柄を購入する場合
- 6ヶ月以上の長期投資を前提にしている場合
この2つくらいで、他は制度信用で構わないでしょう。勿論、これはあくまで一つの考え方でしかありません。
委託保証金とは
信用取引には委託保証金が必要
信用取引は、証券会社からお金や株券を借りて売買するため、相応の担保を入れておく必要があります。この担保を「委託保証金」と言います。
委託保証金は現金、代用有価証券(上場企業の現物株、債権、投資信託)を保証金として使う事が出来ます。現金は100%で評価され、代用有価証券は値動きがあるため、代用掛目と呼ばれる掛け目で評価されます。
一般的な証券会社の場合、
- 国債95%
- 地方債85%
- 現物株80%
- 投資信託80%
といったところです。例えば、現金50万円、現物株100万円分を委託保証金として差し入れた場合、
50万円 + 100万円分 × 0.8 = 130万円
となり、130万円として扱われます。
委託保証金率
委託保証金率とは、取引額に最低必要な委託保証金の割合です。保証金率は証券会社により異なりますが、法律で30%以上と定められており、ネット証券会社も多くは30%程度となっています。
例えば、一株1000円の銘柄を1000株信用買いする場合、取引額100万円ですから、30%の30万円の委託保証金が必要です。
さらに以下の計算式で最大取引額が求まります。
最大取引額 = 委託保証金 ÷ 委託保証金率
先述の例なら30万円 ÷ 0.30 = 100万円となります。委託保証金率が低いほど、同じ委託保証金額でも最大取引額は大きくなります。
委託保証金には最低額がある
委託委保証金は最低でもこれだけは入れて下さいという金額があります。ネット証券などでは、最低額は30万円が多いようです。
委託保証金率が30%であれば、信用取引を行うには取引額の30%以上の委託保証金がなければなりません。この委託保証金率30%の金額が、委託保証金最低額を下回っていた場合はどうなるのでしょうか?
例えば、一株650円の株を1000株信用買いしたいとします。取引額は65万円で、これに委託保証金率30%を掛けると19万5千円ですが、この場合、最低額の30万円の方が優先されます。
つまり、最低額30万円か、取引額に委託保証金率を掛けたいずれか高い金額が適用されます。
委託保証金維持率とは
委託保証金率と委託保証金維持率の違い
これまで委託保証金率というものが出てきました。これは新規で売買する時に、最低必要になる委託保証金評価額を計算する時に用います。一方、「委託保証金維持率」は、すでに持っている建玉を維持するための条件を指します。
代表的なネット証券の1つであるSBI証券の場合、
・委託保証金率 33%
・委託保証金維持率 20%
となっていますが(2024年4月現在)、例えば、1000円の株を1000株信用買いするとします。建て代金は100万円で最低保証金は、
・建て代金100万円 × 委託保証金率30% = 33万円
ですから、最低でも33万円の委託保証金が必要になります。建玉を持った後は、委託保証金維持率が重要になってきます。建て代金100万円の建玉を持ち続けるには、委託保証金の評価額が最低でも、
・建て代金100万円 × 委託保証金維持率20% = 20万円
20万円必要になるのです(この時に比較する委託保証金は委託保証金率の33万円を引く必要はありません)。つまり、建玉を持つために委託保証金率をクリアし、建玉を維持するために委託保証金維持率をクリアしなければならないのです。
建玉と取引額の変動
建玉
信用取引では、信用買いしている状態を「買い待ち」「ロング」と言い、信用売りしている状態を「売り待ち」「ショート」と言います。そして、このような売り買いの状態になっている株を「建玉(たてぎょく)」または「ポジション」と言います。
玉は株を意味し、建てるは新規で買ったり売ったりする事です。例えば、100円の株を1000株、信用買いしたとします。この時、1000株を買い持ちと表現します。購入に掛かった10万円は「建て代金」と呼ばれ、これは信用売りした場合でも同じです。
建玉を持った分だけ取引額が低下する
信用取引の最大取引額は、
差し入れた委託保証金評価額 ÷ 委託保証金率
ですから、委託保証金100万円、委託保証金率30%なら最大取引額は約333万円になります。
この時、一株800円の銘柄を1000株、信用買いしたとしましょう。建て代金は80万円です。この80万円の取引に必要な委託保証金額は、
80万円 × 30% = 24万円
となり、これが委託保証金100万円から引かれ、残りは76万円になります。この残った76万円で取引できる最大額は、
76万円 ÷ 30% = 約253万円
になります。これが信用買いで買い持ちした後の最大取引額になります。この残りの取引額を「信用新規立て余力」と呼びます。
建玉の含み損
信用新規立て余力は新規で建玉を持つと減少しますが、建玉に含み損が出た場合にも減少します。先ほどの例では、
- 委託保証金100万円
- 800円の株を1000株信用買い
していました。この時点で委託保証金の評価額は76万円ですが、買い持ちした株が800円から700円に値下がりしてしまったとします。保有株数は1000株ですから、10万円の含み損が発生しています。
この場合、委託保証金の評価額から含み損10万円が引かれ、
委託保証金76万円 ー 含み損10万円 = 66万円
になってしまうのです。注意しなければならないのは、建玉の含み損は最大取引額から引かれるのではなく、委託保証金の評価額から引かれるという点です。
先ほどの含み損は10万円でしたが、半額の400円値下がりすると40万円の含み損になります。こうなると残りの委託保証金の評価額は36万円で、最低委託保証金額が30万円なら、あと100円も値下がりすれば最低保証金を割り込んでしまいます。
逆に値上がりし含み益が発生したとどうなるでしょうか? この場合、最大取引額が増える事はありません。
二階建てとは
信用取引において、委託保証金として入れた代用有価証券と同じ銘柄の建玉を持つ事を「二階建て」と言います。この二階建ても気を付けなければならず、証券会社によっては禁止している所もあります。例えば、
- A社の株の代用有価証券100万円分
- 1000円のA社の株を2000株信用買い
- 最低委託保証金額30万円
という建玉を持ったとしましょう。建て代金は200万円ですから2倍の取引をしています。この時、株価が30%下がったとしましょう。含み損60万円ですから残った委託保証金の評価額は、
委託保証金100万円 ー 60万円 = 40万円
となり、最低委託保証金額を割り込んでいないように見えますが、二階建ての一階部分である代用有価証券も同じく値下がり(ー30%)しているわけですから、
委託保証金100万円 × 0.7 ー 60万円 = 10万円
で、最低委託保証金額を下回っています。現金ならー30%でも耐えられますが、二階建てだと-23%程度しか耐えられないのです。二階建ては委託保証金を急激に減少させる危険性をはらんでいるため、採用する場合は慎重に検討しましょう。
代用有価証券と二階建て
代用有価証券の値動き
委託保証金を代用有価証券で差し入れている場合は、代用有価証券の値動きにも気を配る必要があります。株式の場合は時価の8掛けですから、時価が変動すれば委託保証金の評価額も変わってくるからです。
例えば、1000円の株を1000株、委託保証金として差し入れたとします。この時の評価額は、
1000円 × 1000株 = 100万円
になります。この株が100円値下がりし900円になったとしましょう。すると、
900円 × 1000株 = 90万円
となり、信用新規立て余力も減少してしまい、場合によっては最低委託保証金額を割り込む事態も考えられるでしょう。
逆に100円値上がりすると、
1100円 × 1000株 = 110万円
となり、信用新規立て余力は増加します。
委託保証金を代用有価証券で賄っている場合は、常に時価で判断されるため、その値動きを追う必要があります。
代用有価証券を売却したら委託保証金額はどうなる?
代用有価証券の株式はいつでも売却可能です。しかし、売却すると委託保証金額はどうなるのでしょうか? 売却すると委託保証金がガクンと減ってしまいそうですが、実際はそんな事はありません。
代用現物株を売却すると売却代金が入り、それがそのまま現金の委託保証金となるか、信用取引口座の預かり金の扱いになります。現物株の時は8掛けでの評価でしたから、売却すると売却時の評価額より委託保証金額がアップします。
反映されるのは翌営業日からが一般的です。しかし、売却当日は8掛けでの評価額になります。
追証とは
差し入れている委託保証金の評価額が減少し、委託保証金維持率を割り込んでしまった場合、証券会社から不足分の保証金を追加で差し入れて下さいと通知があり、不足分の保証金を追証(おいしょう、マージンコール)、通知が来る事を追証がかかると言います。
入金期限は証券会社により異なりますが、「追証発生から翌々営業日の正午まで」が一般的です。期限までに追証を入れなければ強制的に反対売買され、マイナス分は保証金から引かれます。足りない分は現金で入金しなければなりません。
買い方金利と売り方金利
借りたお金には金利がかかる
信用取引の建て代金は借りている、つまり借金ですから金利が発生します。信用買いであれば、借りたお金に「買い方金利」がかかります。年利で表され、それを365日で割った金額が1日あたりの金利「日歩(ひぶ)」と呼ばれます。日歩の計算式は以下です。
建て代金 × 金利 ÷ 365(日) = 日歩
例えば建て代金100万円、買い方金利2.8%の場合、1日あたりの金利は以下です。
100万円 × 2.8% ÷ 365日 = 約77円
信用取引で買いにせよ売りにせよ、建玉(ポジション)をとった場合、支払う金利の計算式が以下です。
日歩 × 建玉を維持した日数 = 支払う金利
上述の例なら、建玉を30日間持ったとすると、30日×77円で2,310円の金利を支払います。売却時点で10%値上がりしていれば、受け取る金額は以下です。
売却代金110万円 ー (建て代金100万円 + 合計金利2,310円) = 97,690円
厳密には手数料などのコストも掛かります。制度信用と一般信用の金利を比べると、一般信用が高い証券会社がほとんどです。
下が代表的な証券会社の制度信用と一般信用の金利一覧です。
| 会社名 | 制度信用の買い方金利 | 一般信用の買い方金利 |
|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 2.75% | 2.00% |
| SBIネオトレード証券 | 2.30% | 2.75% |
| SMBC日興証券 | 2.50% | 3.00% |
| 岩井コスモ証券 | 2.69% | 3.69% |
| 岡三オンライン | 2.60% | 2.80% |
| マネックス証券 | 2.80% | 3.47% |
| SBI証券 | 2.80% | 2.80% |
| 楽天証券 | 2.80% | 2.80% |
| auカブドットコム証券 | 2.98% | 2.79% |
| 松井証券 | 3.10% | 4.10% |
2024年4月現在。これは一般顧客向けで、大口顧客向けには別のプランが用意されています。
日数計算には気を付ける
買い方金利は建玉を精算するまでの日数分かかりますが、この日数はカレンダーで数えた受渡日で決まります。
例えば、月曜日に信用買いすれば受渡日は4営業日目の木曜日になります。これを買った翌日の火曜日に売却したとしましょう。買いで受け取るのが木曜日、売りで手放すのが金曜日ですから、金利はこの2日間分かかるという計算になります。
しかし、もし火曜ではなく水曜日に売却したらどうなるでしょう。まず受け渡しが木曜日、手放すのが土曜日ですが土日は休みですから、実際は翌週の月曜日に売却が約定します。つまり、木、金、土、日、月の5日分の金利が発生するという事です。
そこまで気にする事ではありませんが、大型連休などには注意が必要です。
制度信用には証券金融会社の金利が含まれている
制度信用ではお金や株券を証券金融会社から借り入れており、当然、証券金融会社にも金利を支払う必要があります。
この証券金融会社分の金利は、証券会社が提示している金利に含まれており、別途、支払う必要はありません。
本来、信用売りは金利が貰える
信用売りというのは、売りから入っているのですから、本来、売却代金を受け取る事が出来ます。しかし、それを決済するまで受け取らないわけですから、これはお金を貸している状態になり、お金を貸す以上、金利が貰えるはずです。
この貰える金利を「売り方金利」と言い、仕組みの上では信用売りしている投資家は、売却代金に応じた金利が貰えるのです。しかし、現在の売り方金利はゼロですから、信用売りをしても売り方金利は貰えません。
貸株料とは
貸株料は空売り規制で導入された
信用売りはお金を借りていないため、金利は取られませんが、株券を借りているため「貸株料」というコストを支払わなければなりません。
これは2002年5月7日に、空売り規制の一環として導入された制度で、それ以前にはこのようなコストは存在しませんでした。貸株料は信用売りした日から返済日まで、建て代金に対する貸株料の日数分がコストになります。
例えば、貸株料が1.15%、建て代金100万円の場合、一日あたりの貸株料は、
建て代金100万円 × 1.15%(0.0115) ÷ 365日 = 約32円
となります。売建玉を持っている期間が30日なら30×32円で960円となります。貸株料はどの証券会社もほぼ1.1%か1.15%のどちらかです。中には一般信用で信用売り出来る証券会社もありますが、一般信用での貸株料は制度信用よりも割高が普通で、1.5%~2%が多いようです。
信用買いで貸株料は貰えない
信用買いしている人は、買った時点で株券を受け取らず、株券は証券会社が店内食い合いという形で信用売りしている人に貸し出しています。貸しているから借り手(信用売りしている投資家)から貸株料を貰えているわけです。
その株券を信用買いしている投資家が出しているのですから、信用買いしている人が貸株料を貰えそうなものですが、実際は貰えません。これは仕組みとしてそのような制度になっているのです。
逆日歩(ぎゃくひぶ)とは
信用売りのコスト逆日歩
信用売りのコストとして貸株料が挙げられますが、これ以外にも逆日歩(ぎゃくひぶ)、もしくは品貸料と呼ばれるコストが発生する場合があります。逆日歩は、信用売りしている株数が信用買いしている株数よりも多くなり、証券金融会社が株不足になった時に発生します。
信用取引は買いと売りがあり、まず証券会社自体で買い売りを相殺(店内食い合い)しますが、足りない分は証券金融会社から借り入れます。信用取引は株券を借りて売却する取引ですから、まず証券会社は自社でその株を用意しますが、無理な場合は証券金融会社に借ります。
しかし、信用売りが多過ぎて証券金融会社でも全ての株券を用意出来ない自体も起こりえます。そういう時は、他の機関投資家(銀行、保険会社など)から有料で調達します。この時に発生するコストは投資家が負担し、それが逆日歩です。
本来なら、信用売りしている側が売却代金を貸しているわけですから、日歩(金利の日割り分)が貰えるはずですが、株不足になると逆にその日歩を払うため逆日歩と言います。
例えば、一株あたり5銭(0.05円)の逆日歩がついた銘柄を1000株信用売りしたとします。
1000株 × 5銭(0.05) = 50円
で一日あたり50円の逆日歩が発生する事になります。一ヶ月(30日)ポジションを持っていれば、1,500円のコストが掛かるわけです。
逆日歩の発表は翌日になる
逆日歩がつくかどうかは、証券金融会社の状況によりますから、株不足(逆日歩がつく)かどうかはその日の貸出残高を計算するまで分かりません。そのため逆日歩がつくかどうか、いくらつくのかは翌日にならないと分かりません。
つまり、新規で信用売りする時には、逆日歩は予想出来ないという事です。
信用買いしている銘柄の逆日歩
信用買いしている銘柄に逆日歩がついたらどうなるのでしょうか? この場合、投資家は逆日歩分のお金を受け取る事が出来ます。
例えば、何かの株を1000株信用買いしていたとしましょう。この銘柄の1株あたり5銭の逆日歩が10日ついたとします。すると、
1000株 × 5銭(0.05)× 10日 = 500円
となり、500円受け取る事が出来ます。逆日歩に金額によっては狙い目とのなるので、信用買いする時は参考にされると良いでしょう。
信用取引における配当金の扱い
信用買いしていた時の配当金
何かの株を信用買いしたとしても、直接、現物株を購入したわけでもなく、代金もまだ支払っていない状態ですから、この時点では後でその株価で現物株を現引きする権利を得ただけです。いわば仮の株主になった状態で、株主総会の議決権もありません。
では、投資家が信用買いした株の株主は誰なのでしょうか? それは株券を預かっている証券会社(もしくは証券金融会社)になります。そして、買い持ちしている投資家がポジションを清算すると、ポジションを持ってから清算するまで自分が株主であった事が確定します。
これは即ち、信用買いしていた投資家は配当を受け取る権利があったという事になり、実際に配当金が支払われた時、証券会社は配当金相当額の配当落調整額(はいとうおちちょうせいがく)を投資家に支払います。勿論これは、権利付最終売買日をまたいで信用買いしていた人のみが対象です。
ちなみに、株主優待は受け取れません。
信用売りしていた時の配当金
信用売りしていた場合は事情は異なります。信用売りしていた投資家は「借りた株券を他人に売った」形になります。そして、その株を買った投資家は、この時点で株主としての権利を得るのです。
しかし、信用売りした人に株券を貸した人(証券会社や証券金融会社)も、株券を貸しただけであり権利まで手放したわけではありません。こうなると、株を購入した投資家は配当金を貰う権利があり、信用売りした人に株券を貸した人にも配当金を受け取る権利がある事になります。
株券は一人分しかない以上、これは矛盾しています。そこで、株券を貸した人に支払う配当落調整額は信用売りした投資家が負担する事になっています。ポジションを清算したときに配当落調整額が引かれ、その時点で配当金が分からなければ後々決定した時点で差し引かれます。
電話審査で聞かれる項目
審査基準
信用取引は一種の借金であり、レバレッジを掛けるためリスクも高くなります。そのため誰でも口座開設出来る分けではありません。基準は公開されていないため、厳密に分かりません。
証券会社に口座開設する時に、職業、金融資産、運用方針、株の取引年数などといった項目を記入したと思いますが、これらも影響しますので事前に最新の情報に更新しておきましょう。
無職だと審査が通りづらいと言われますが、間違いではないまでも、より重要なのは金融資産の多寡であり、取引経験や金融資産がしっかりあれば無職でも口座開設可能です。
対面の証券会社よりネット証券会社の方が審査は緩いと言われており、
・預かり資産最低30万~100万円以上
・取引年数1年以上
程度で口座開設可能のようです。あくまで一般論ですから保証は出来ません。これ以外にも、投資方針:利回り・安定重視、資金の性格:余裕資金、信用取引:1年以上などが望ましいでしょう。
現在は競争が激しく、信用取引の高い金利を支払ってくれる顧客は有難い存在ですから、昔と比べてハードルは下がっているようです。しかし、まるで取引経験の無い人が、いきなり信用取引を申請してもまず受からないでしょう。
電話審査
証券会社によっては信用取引口座を開設するにあたって、投資家に電話で信用取引の理解度を確認してきます。以前はそれが一般的でしたが、最近はWeb審査のみで口座開設出来る証券会社も増えてきたようです。
内容はそれほど高度なものではなく、あくまで基礎知識のおさらい程度で難しくはありません。時間は5分程度のところもあれば、30分も掛かるところもあるようです。証券会社によってはだた「はい、はい」と答えるだけで良いところもあります。
下記は質問と回答の一例です。サンプルとしてSBI証券を前提としています。
投資額以上の損失が出るリスクは理解しているか?
はい、理解しています。
制度信用と一般信用の違いは何か?
制度信用は、返済期限があり最長で6ヶ月、さらに売買出来る対象銘柄が決まっています。一般信用は、各証券会社毎に異なり多くは無期限で、対象銘柄は基本的に上場銘柄の全てです。多くの証券会社では制度信用で出来る空売りが出来ません。
委託証拠金維持率とは何か?
委託保証金維持率はポジションを維持するための条件です。SBI証券の委託保証金維持率は20%です。
二階建てとは何か?
二階建てとは、委託保証金として差し入れている代用有価証券と、同一の銘柄を信用取引で買い建てる事です。
代用有価証券の掛け目は?
8掛けで80%です。
逆日歩とは何か?
信用売りしている株数が信用買いしている株数よりも多くなり、証券金融会社が株不足になった時に機関投資家などから有料で株を調達します。その時に発生するコストは投資家が負担しますが、それが逆日歩です。
追証とは何か?
差し入れている委託保証金の評価額が減少し、委託保証金維持率を割り込んでしまった時、不足分の追加保証金の事です。
追証がかかったらどうするのか?
証券会社により決められた期限までに追加保証金を入金します。入金期限までに追加保証金を入れないと強制的に決済され、マイナス分は委託保証金から差し引かれます。それでも足りない場合は現金で入金しなければなりません。
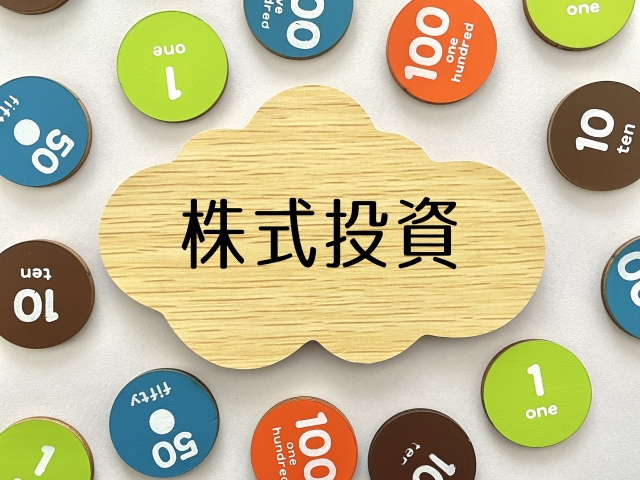
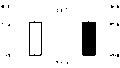

コメント